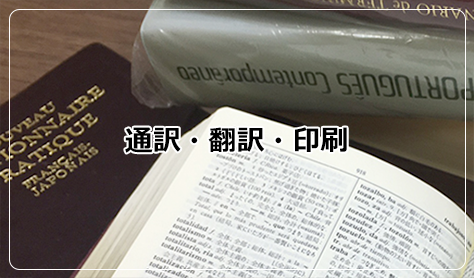事業・実績
NEWS
2025.12.01
2025.08.06
2025.04.16
現地リポート
2024.12.16
調査部 後藤佑真
カンボジアの観光地として有名なシェムリアップ。ここは、世界遺産に指定された数多くの歴史的建造物がありますが、私が特に印象に残ったのはアンコールワットとタプローム寺院です。
朝日が昇るアンコールワットには、早朝にもかかわらず大勢の観光客たちが集まり、遺跡を背に昇る太陽を拝みます。私が訪れた日はやや曇り空でしたが、朝日とともに池に浮かぶ「逆さアンコールワット」も見ることができました。ちなみにアンコールワットの頂点である中央塔から朝日が見られるのは、年に2回の春分の日と秋分の日だけだそうです。
アンコールワットの中を巡ると、遺跡自体は石でできており、その彫刻が非常に細かく繊細であることがわかります。壁面には、戦いの模様や当時の生活の様子が描かれており、歴史を感じさせてくれます。近くのお寺からは、読経とお祈りの声が聞こえ、カンボジアの人々の信仰心の強さを感じることができました。カンボジアの国旗にはアンコールワットが描かれていることからも、この遺跡が国の象徴であり、重要な存在であることがわかります。
アンコールワットの朝日
アンコールワットの遺跡
タプローム寺院では、大木に飲み込まれてしまった遺跡を見ることができます。遺跡全体がまだきちんと修復されず、崩れた状態のままの箇所もありますが、遺跡や崩れた石に生えている緑色の苔はとても奇麗で神秘的です。乾季に入り暑さが増す11月からは、苔は見られなくなるそうです。ここは数々の映画の撮影スポットとしても有名で、選ばれるのも納得できる場所です。
この地域一帯に広がる遺跡群は広大で、気温も高くなるため、訪れる際には日差し対策や飲み物の準備が大切だと感じました。
タプローム寺院1
タプローム寺院2
カンボジアのクメール料理は、歴史的にもベトナムやタイ料理の影響も受けているようですが、タイ料理よりもあっさりした印象で、食べやすくて美味しいです。
屋台では、日本では中々見かけない食べ物にも挑戦しました。勇気を出して挑戦したカエルの丸焼きは意外にも美味しく、クセがなくて驚きました。見た目は少しドキドキしますが、味は想像以上に繊細で、鶏肉に近い味わいです。
カエルの丸焼き
私の中での一押しの食べ物は、ノムタナオと呼ばれる蒸しケーキです。ノムタナオの材料はとてもシンプルで、ヤシの実の粉、ココナッツミルク、砂糖だけです。食感はモチモチしていて、ほんのり甘い生地の中にトロリとしたココナッツミルクが入っています。出来立ては思わずやけどしそうになるほど熱々でしたが、その熱さが出来立てならではの美味しさを引き立てています。ノムタナオはカンボジアの市場でも売られているそうですが、ココナッツミルクが入ったものが食べられるのはシェムリアップだけだと、同行した現地スタッフの方も言っていました。ノムタナオは、大切な家族の行事や地域のお祝いにも深く関わっている伝統的なお菓子だそうです。お店の奥では、大量に積み上げられたヤシの実を一つひとつ手作業で剥くところから、最終的に蒸し上げるまでの一連の工程を見ることができました。
ノムタナオ
市場の様子
シェムリアップでも多く見かけるヤシの木ですが、カンボジアでは様々な形に加工され、広く流通しています。木の幹は建材や家具に使われ、実はオイルやジュースに加工され、葉っぱは家の屋根や食器、帽子、さらには祭りの装飾品などに利用されています。このようにヤシの木は、カンボジアの生活にとって重要な役割を果たしています。私もお土産として、世界一美味しいとも言われるカンボジアの胡椒の実を擂ることのできる、ヤシの木でできたすり鉢を購入しました。(胡椒は買い忘れてしまいました…)
すり鉢
カンボジアの人々はどこへ行っても、温かく優しい笑顔と挨拶で迎えてくれて、とても礼儀正しく親しみやすい方が多いことが印象的でした。 国の更なる発展を願いつつ、同時に歴史的な遺跡や文化が変わらずに残ってほしいという思いを抱きながら、カンボジアを後にしました。シェムリアップは、歴史と自然が織りなす神秘的な場所で、また数年後に訪れたいと思える場所となりました。カンボジアはどんな面でも新しい発見があり、決して飽きることのない国です。もし訪れる機会があれば、ぜひその歴史や文化、人々との触れ合いを楽しんでほしいと思います。
2024.10.25
調査部 平野太一
日本から飛行機を乗り継ぐこと約20時間。日本を出た日は猛暑日だったが、気温の低さと人々の服装で、季節が逆の南半球に来たことは簡単に認識できた。
ここはアフリカ大陸最南にある南アフリカ共和国、ヨハネスブルクである。
この記事では、主に南アフリカの簡単な歴史と生活、名物(食事)について説明をしようと思う。個人的見解も含まれているので間違いがあるかもしれないが、主に私が現地で見て、聞いたことを元に作成している。
ヨハネスブルクの街並み
ネルソンマンデラ国立博物館
南アフリカと聞いて、日本では主に人種隔離政策の「アパルトヘイト」で耳にしたことがある方が多いのではないかと思う。1994年、今から20年前、アパルトヘイト体制撤廃後初の全国民、全人種が参加した総選挙が行われ、アフリカ民族会議(African National Congress、ANC)の代表であったネルソンマンデラ氏が大統領に就任し、黒人隔離政策であったアパルトヘイトは終焉を迎えた。その後、20年にわたり、ネルソンマンデラ氏が率いたアフリカ民族会議(African National Congress、ANC)が議会の第一党を維持している。
歴史的には、17世紀ヨーロッパ人の入植以降白人系、黒人系、カラード(混血)、アジア系等、様々な人種が暮らしているこの国で、ネルソンマンデラ氏は「虹色の国」を目指すという宣言をした。彼は自身がアパルトヘイト政策により、27年もの間投獄されていたにも関わらず、人種による対立ではなく、多様な人種の融和による、国の形を目指した。その意思は現在でも引き継がれ、白人系、黒人系を主として様々な人種がそれぞれを尊重しながら生活をしている。そのため現在南アフリカは、大別すると4人種9部族から構成され、世界最多の11種の公用語をもつ。
南アフリカを語る上で、歴史の背景を認識することはとても重要である。南アフリカに関する歴史的、政治的な記事や書物は専門家により多く存在するため、ここではこれ以上記載しないことにする。
私は新しい国に行った際、まずその国の名物を聞き食すことにしている。南アフリカに到着し最初に「この国の名物は?」と聞いたら、「ブルボス」・「ビルトン」・「ワイン」と言われた。名前だけでわかったのはワインだけであった。 1つ目の「ブルボス」とは、ソーセージのことで、ドイツ系の移民が持ち込んだとされている。このとても太くて長いソーセージをとぐろ状に成型し、バーベキューで焼き、食べることが多い。味はスパイスが効いていてとてもお酒に合う味となっている。
2つ目の「ビルトン」とは干し肉のことでありビーフジャーキーのような味わいと触感でこちらも酒にはとても合う。(肉製品のため残念ながら日本にはお土産として持ち込めないが・・・)南アフリカではスーパーマーケットでも簡単に購入できるが、専門店ではダチョウやワニのビルトンも入手できるようなので、南アフリカに渡航した際は探してみるといいかもしれない。
最後にワインであるが、日本でもインターネットやワイン専門店では南アフリカのワインを目にすることができる。「ピノタージュ」という品種が有名であり、この品種は南アフリカで品種改良された品種となっており、スーパーマーケットやワイン専門店では数多くのブランドを楽しむことができる。また、ブドウ畑の中にあるホテルに滞在し、滞在中ワインと食事に楽しむことができるプランもあるようで、ワイン好きの方にとっては魅力的ではないかと思う。 以上の3つは日本人の口にも合う味となっており、南アフリカへ訪問することがあればぜひ食してほしい。
富裕層が住む住宅
貧困地域の写真
現地での生活についてだが、基本的なインフラは整っており、日本と変わらない生活が可能である。近年電気インフラの問題により計画停電が頻繁に発生しているが、この計画停電もスマホのアプリで自分の生活している地域は何時から何時まで停電するということを事前に知ることができ、備えることができる。各家にはソーラーパネルを備えている家が多く、停電中も最低限の電力はそのような自家発電で賄っている家庭が多い。ただしこれは中流家庭以上であり、収入が低い家庭では、インフラ設備が備わっていないところも多いと聞いた。このようなところでは、世界最大のジニ係数となってしまっている南アフリカ社会の実情を伺うことができる。
また、南アフリカといえばラグビーである。イギリス植民地時代から白人のスポーツの代表であったものの、最近では黒人初のキャプテンや、プレイヤーが増えており、白人系のパワーと黒人系のスピードを融合したチーム構成となっている。2019年、2023年のワールドカップを連覇、2024年の南半球の国々で行われているチャンピオンシップも制覇し、現在名実共に世界最強チームとなっている。
日本のラグビーリーグにも南アフリカの選手が在籍しているので、興味がある方は日本で観戦することが可能である。
まとまりの無い内容のレポートとなってしまったが、南アフリカは犯罪率が高く怖いというイメージを持つ人が多いと思う。確かに犯罪率などは高く、日本と比べると危険度が高いことは間違いない。しかし、私が南アフリカで出会った人々はとても温和で、真面目で楽しい方ばかりであった。
正しい情報を入手し、正しく恐れ、準備すればどの国でも楽しく過ごすことができると私は考えているので、南アフリカに興味がある方はぜひ訪問することを検討してみてほしい。
2022.12.20
調査部 研究員 清水信子
ネパールは中国とインドという二大国に挟まれた国です。北海道の約1.8倍の土地は、エベレストをはじめとするヒマラヤから南部のタライ平原までダイナミックな変化にとんでいます。また、ヒンドゥー教や仏教の寺院、仏陀がうまれたルンビニ、野生動物公園等、見どころがたくさんあります。そんなネパールに人材育成奨学計画準備調査(https://www.jica.go.jp/activities/schemes/grant_aid/summary/JDS.html)のために訪れました。
今回はネパール料理について紹介させていただきます。
(写真1)
まずは、ネパールを代表する定食のダルバート(दालभात)です(写真1)。ネパール語でダルとは豆のスープを、バートはコメを意味します。南アジアの料理は辛い印象を持たれますが、この豆のスープは辛くないため日本人にもとても食べやすい料理です。ただし、副菜としてついている、漬物(アチャール)は辛いです。写真のダルバートのように辛さを和らげるためにヨーグルトがついているお店もあります。
次に、ネパール版餃子のモモをご紹介します。見た目はまさに餃子ですが、中身に香辛料が入っているので私達の知る餃子とは一味違います。蒸したSteam momo(写真2)、揚げたFried momo(写真3)、焼いたKothey momo(いわゆる焼き餃子)、スープの中に入ったJhol momo(写真4)、完全に餃子の上部の皮を閉じずに蒸し、開いている箇所からソースをかけて楽しむOpenmomo(写真5)など沢山の種類があります。驚くことにデザートモモというスイーツまであります。日本でモモを提供しているインド、ネパール料理店もありますので、是非一度お試しあれ!
(写真2)
(写真3)
(写真4)
(写真4)
参照:
Bota Mo:Mo. (2022a) Probably the best veg mo:mo — at Botaबोता Food & Restaurant. Available at: https://www.facebook.com/botarestaurant/photos/2903177649977840
Bota Mo:Mo. (2022b) PERFECT FOR THE WEATHER! WE ARE OPEN AT KAMALPOKHARI— at Botaबोता Food & Restaurant. Available at: https://www.facebook.com/botarestaurant/photos/a.1681932905435660/2900700806892191/
Bota Mo:Mo. (2022c) — at Botaबोता Food & Restaurant. Available at: https://www.facebook.com/botarestaurant/photos/2902333706728901
Bota Mo:Mo. (2022d) — at Botaबोता Food & Restaurant. Available at: https://www.facebook.com/botarestaurant/photos/2897971040498501
2022.06.02
調査部 研究員
“She sleeps like a cocoyam”「彼女はヤムイモのように眠っている。」
ゆくりなくも、ガーナへの道中かたわらにあった小説「Ghana must go」で遭遇したこの印象的な喩-ヤムイモのような眠り-から、本稿を始めたい。
ガーナマストゴー(ガーナ人は出ていかねばならない)、この80年代に起きたナイジェリアにおけるガーナ労働移民排斥命を冠する小説は、21世紀にも清算されずに残った孫世代のディアスポラの新たなビオスを、後述する作者自身の出自・経験を通じ提出している。同作は、父に捨てられ世界中へ離散した家族が、その父の死とともにガーナに集い、喪の作業を通じて再生を遂げる物語を縦糸に、Toni Morrison あるいはSalman Rushdieといった先達への周到な目配せを細部に広げながら、新たなポストコロニアル文学として見事なエクリチュールを紡いでいる。読む者は、その冒頭、一家の領袖として罪を負った父が、美しい庭で悔恨のうちに静かに息を引き取る傍ら、何も知らずにベッドで眠っている二番目の妻-まさにヤムイモのような眠り-との対比の、息を飲むような描写に出会うこととなる。
ガーナとナイジェリアのオリジンを持ち、イギリスで育ち、ローマやアメリカに渡るという、ディアスポラの当事者たる著者、Taiye Selasiは、同作の上梓以前に、「Afropolitan」という造語を駆使し、新たなノマディズムとして、ネーション=ステートの夥しい抑圧の記憶から離れた、新たなる「Region」としての繋がりを唱えたものだが、それはフランツ・ファノンの生きた時代の抑圧への抵抗のための「Pan₋African」から、新しい世代の「Afropolitan」への移行を目指すものとして、今作にも色濃く反映されている。
私は目指すガーナにまつわるこの小説に、免疫自体のシステムが自他の境界を無理やりに策定させ、誰でも潜在的な敵(ホスティル)としてしまう状況を露呈させている中(それはあらゆる境界による分断とパラレルである)、Foreignerとして移動することの意味を見出させるものとして、大きな励みとなった。そして同作で繰り返し描かれるまばゆいガーナの陽光そのものを通し、新しい視点を得ることが大きな目的となったのである。
紛争地の上空を避けながら、巨大な金属の鳥は長い迂回の果て、深夜アクラへ舞い降りたが、実際にガーナの強い陽光を初めて認識したのは、まさにヤムイモのような眠りから覚めた後のことだった。
滞在先の”コロニアル”様式のホテルでは、いたるところに極楽鳥花の切り花が、無造作に、しかし艶めかしく目を惹きつけるように生けられており、強い陽光そのものの表徴であるような花に、ふと、晩年にアルジェリアからガーナへ初の大使として派遣されたファノンの言葉-「私は真に地上における太陽の一滴である。」(「黒い皮膚、白い仮面」)-を思い浮かべた。
その後、強い陽光のなか、さまざまな国籍を持つ自動車が、めいめいのやり方で土埃を巻き上げる道で、往来する人々、路上の商人たち、舗装作業に従事する青いツナギの受刑者、陽にあぶられあられもなく眠る人、唐突な笑い、そして「Ghana must go bag」(注)を両手いっぱいに持ちどこかへ向かう人を見るにつけ、それら「太陽のひとしずく」たち、ファノンの言う「太陽の湧出物をすべて身に引き受ける」彼らの輝かしさと、Foreignerへの探るような曖昧でやさしいまなざしに触れ、敵(ホスティル)と客(ホスピス)とは同じ語源を持つことに改めて気づくのだった。
帰路にて筆者は、晴れて機内濃厚接触者となり、つまり社会的免疫システム上のホスティルとなり、新宿のホテルで8日間の滞在を行う“隔離客”となるが、ふとテレビを付けると賈 樟柯「長江哀歌」が映し出されていた。
ダムに沈んだ町を巡り、別れた妻と娘を探すというその映像作品は、とりもなおさず巨大な一国内のディアスポラ、地に生きる「太陽のひとしずく」たちの彷徨を描いていた。
今回の道行きでの思考と重なる、その不思議な偶然の符号も最後に書き添えておかねばならない。
(注)Ghana must go bag 誰しも一度は目にしたことのある青赤チェックのビニール製バッグは、「Ghana must go」が発令され、その短い通告の際、ガーナ労働者たちが慌てて荷物を詰めなければいけなかったことから、この愛称で呼ばれている。